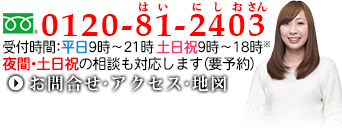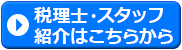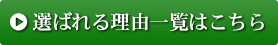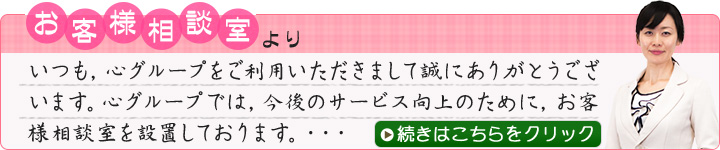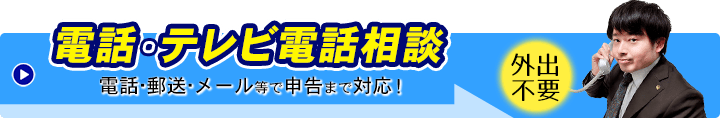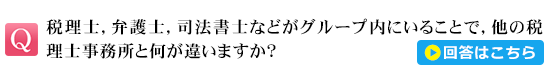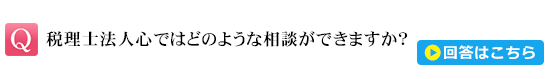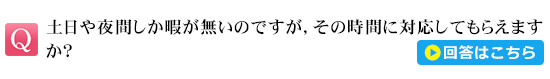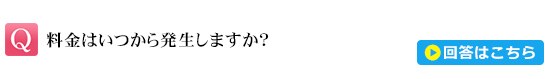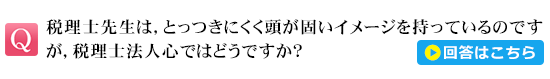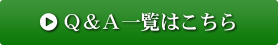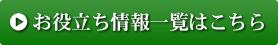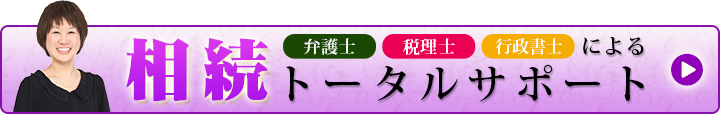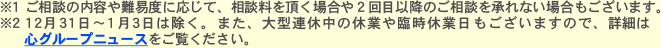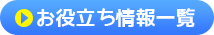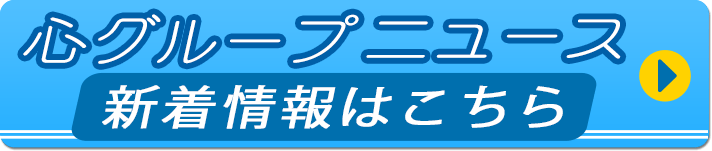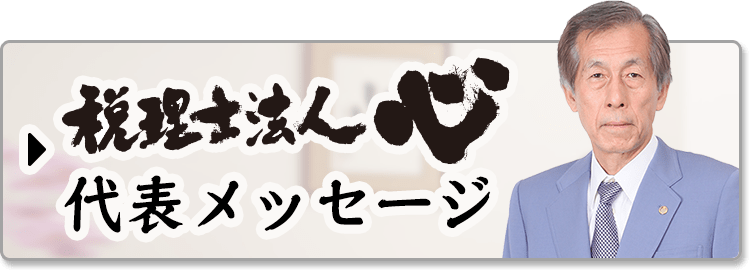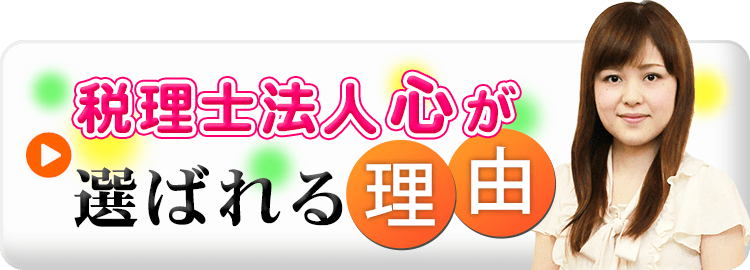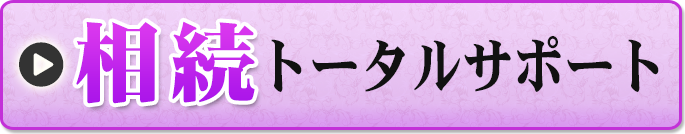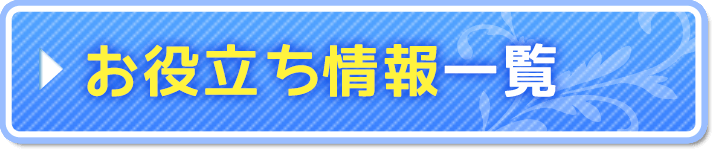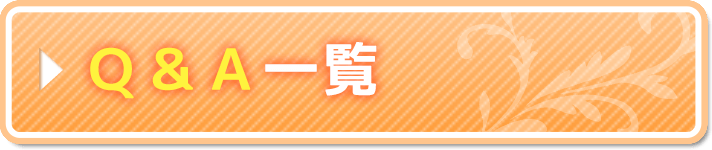-
1税務官庁勤務歴40年の元税務署長税理士が所属
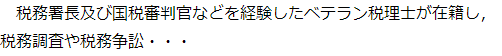 続きはこちら
続きはこちら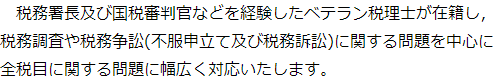
-
2弁護士兼税理士が税務署との交渉や税法解釈を担当
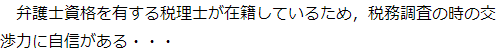 続きはこちら
続きはこちら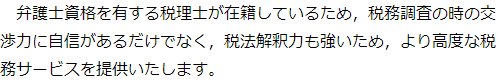
-
3心グループの300名の正社員が組織力でバックアップ
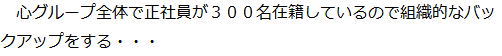 続きはこちら
続きはこちら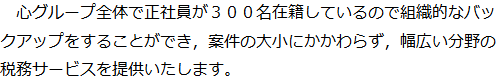
-
4弁護士・社労士と連携してトータルサポート
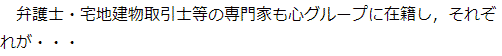 続きはこちら
続きはこちら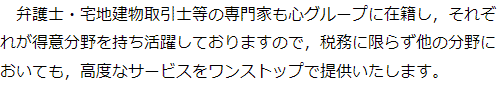
-
5土日祝・夜間の相談も対応
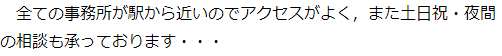 続きはこちら
続きはこちら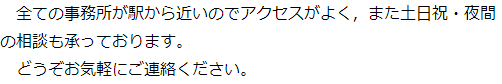
名古屋で税理士をお探しの方はご相談ください
お悩みの内容を丁寧にお聞きし、適切な解決に向けて尽力いたします。税に関してお困りの方は、当事務所までご相談ください。
-
税理士を選ぶ際にポイントとなることとしては、以下が挙げられます。①依頼する分野に詳しい税理士を選ぶ、②顧問料金と顧問業務の内容を確認する・・・続きはこちら
-
まずは、事務所にご来所いただいて無料相談を行わせていただく事務所が多いようです。ただ、事務所の中には初回の相談から・・・続きはこちら
-
税務署は、国税庁の下部組織として設置されている行政機関です。税理士は、国家試験を通った専門資格を有する民間の専門家です。税務署で・・・続きはこちら
お役立ち情報
税務のことなどについて知りたいという方の役に立つ情報をまとめてあります。順次更新を進めて参りますので、気になることがある方はご覧ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2026年2月6日
専門家
税理士と公認会計士の違い
税理士も公認会計士も会計に関わる仕事を行う点は同じですが、この二つは異なる国家資格であり、法律上、それぞれの独占業務が決まっています。税理士の独占業務は、税務書類の作成・・・
続きはこちら
2025年4月4日
所得税
所得控除や税額控除を受けるには
所得税の計算の際には、年間の収入から所得控除額を差し引いて算出される課税所得金額に税率をかけて税額を出します。所得控除というのは、税率をかける前の課税所得から差し引か・・・
続きはこちら
2025年3月5日
所得税
確定申告の基本的な流れとポイント
病院や調剤薬局での処方を受けた金額が年間で10万円を超える場合には、医療費控除の適用を受けられ、所得税が安くなります。ですので、病院や調剤薬局から受け取った領収書や・・・
続きはこちら
2025年2月19日
相続税
相続税の対象となる財産
相続人は、被相続人のすべての財産、権利、債務を引き継ぐことになります。財産を引き継ぐと、金銭的に価値を見積もることのできる財産のすべてに対して相続税が課税されます。具体的・・・
続きはこちら
2024年12月16日
贈与税
贈与税の配偶者控除の特例
夫婦間の贈与に関して、特例があると聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。結婚してからの期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための・・・
続きはこちら
2024年12月3日
記帳代行
税理士に記帳代行を依頼すべき理由
個人事業主の方の場合、コストをできる限り削減するために、ご自身で記帳から確定申告までを行っている方が多いと思います。事業に関するお金の流れを自分でも把握しておくことは、事・・・
続きはこちら
2024年11月15日
相続税
相続税の計算方法
相続税の計算は、一般的に、以下のような流れで行います。①遺産の価格を求める②基礎控除額を計算する③実際に課税される遺産の総額を求める④相続人全員で納める相続税の総額を計・・・
続きはこちら
お役立ち情報の更新情報
税のお悩み等に関する情報を随時更新してまいります。税に関してお悩みの方は、こちらもご覧になり、お役立ていただけますと幸いです。
名古屋駅徒歩2分の事務所
当法人は駅の近くに事務所を設けております。お客様のご相談に対し、よりよい解決方法をご提案できるよう努めますので、まずは一度相談ください。
税理士の業務内容の違い
1 個人の確定申告を受ける税理士と受けない税理士

税理士のなかには、個人事業主からのご依頼は受けないという税理士もいます。
これは、法人の申告と異なり、個人の確定申告業務は、毎年3月15日までに申告が必要となるという申告期限が定められているため、業務負担を均一化・平均化することが非常に困難だからです。
徹底している税理士事務所のなかには、顧問先の社長の確定申告ですら受けないというところもあります。
2 顧問業務が中心の税理士とスポット業務が中心の税理士
顧問業務が中心の税理士とは、所得税・法人税・消費税などの記帳代行を伴い月次の監査を行い、顧問先に決まったタイミングで月次の資料を作成して月次推移表を作成する業務を行っている税理士です。
これに対し、スポット業務が中心の税理士とは、贈与税・相続税などの申告業務を行うことを中心としている税理士です。
後者の税理士があまり多くないのは、スポット業務は偶発的な事情によって生じるため、税理士事務所としての収入が安定化しづらく経営の指標がたてづらいことが理由の一つです。
3 記帳代行まで行う税理士と記帳代行は受けない税理士
記帳代行を行う税理士は、お客様から資料をお預かりし、税理士事務所側で仕訳の入力業務を行っています。
他方で、税理士のなかには、請求書、領収証や通帳などのいわゆる記帳代行業務は行わない税理士もいます。
このような税理士は、記帳代行指導として、記帳代行そのものは顧問先の担当者が行うことを前提とし、定期的にその監査・チェックを行い、誤っている仕訳をしている場合はその修正と指導を行っています。
前者の税理士の場合は、すべて丸投げすることができるので、お客様は非常に楽で便利ですが、記帳代行報酬がかかります。
後者の場合は、顧問料は安く済ませることができるかもしれませんが、自ら領収証等の資料を誤りなく仕訳することが求められることになるという違いがあります。
節税対策に詳しい税理士を選ぶポイント
1 分野に特化しているか

税金には、所得税、法人税、消費税、相続税など、様々な税分野があります。
適法・適切な節税対策を行うためには、法改正や通達の頻繁な改正にも対応できている必要があります。
法改正や細かな通達の改正まで把握するためには、日常的にその税分野を取り扱っていなければなかなかできません。
ですので、その分野に特化しているかどうかを確認した方が、より節税につながる方法を知っている可能性が高いといえます。
2 保険・不動産を使った相続税対策が提案できるか
相続税対策を行う場合には、生命保険金と不動産の活用を検討することは必須と言っても過言ではありません。
法定相続人の人数×500万円相当の死亡保険金に入るだけで、法定相続人の人数×500万円までは非課税となります。
また、現金預貯金を不動産に変え、その上に賃貸アパート建てるだけで、現金預貯金時の半分近くまで評価額を下げるような不動産の評価減を利用した相続税対策等があり得ます。
このような相続税対策を提案し、実行することができるのは、例えば、同じグループに所属する法人が保険会社や不動産会社を有しており、トータルでサポートすることができるような場合です。
したがって、同じグループ内に保険会社や不動産会社を企業しているかどうかも一つのポイントになります。
3 経営革新等支援機関の認定を受けているか
例えば、事業のために機械設備などを購入したり、リースで契約した場合、金額にもよりますが経営力向上計画の認定を受けることができることがあります。
経営力向上計画の認定を受けると、減価償却の特別償却を受けることができたり、一定金額まで税額控除を受けることができるようになります。
ただ、経営力向上計画の認定を受けるためには、ご自身で経済産業局に所定の申請書類や添付資料を提出するか、経営革新等支援機関に作成を依頼する必要があります。
税理士事務所のなかには、経営革新等支援機関の認定を受け、経営者からこのようなご相談を受けた場合には速やかに対応することができるよう準備をしているところもありますので、このようなお手伝いができる事務所かどうかも、節税対策に詳しい税理士を選ぶポイントといえます。
税務相談をする税理士の選び方
1 相談したい税目に詳しい税理士を選ぶ

税理士はすべての税金の専門家ではありますが、普段あまり取扱わない税目に関しては、専門家といえどもそれほど詳しくないことも多々あるのが実際のところです。
所得税、法人税、消費税、酒税、固定資産税、住民税など、税理士が扱う税目は非常に多岐にわたりますので、まずはご自身が何の税金に関してご相談されたいのかを明確にしたうえで、その税目に詳しい税理士を探すことをおすすめします。
2 法令の改正に詳しい税理士を選ぶ
税金に関する法令は、毎年のように変更されますし、年度の途中でも政治の動向によって政策的に新たな制度ができることも少なくありません。
こうした情報を知らずに対応すると、誤った内容や対応となってしまい、場合によってはペナルティを課されてしまうおそれがあります。
したがって、法令や通達の改正に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。
3 業種に詳しい税理士を選ぶ
税金に関するルールは、業種を問わず共通しているものもありますが、これまでの慣例、実務の積み重ねによって、主に特定の業種だけに適用される法令や通達も少なくありません。
本当はもっと税金を安くすることが可能であったにもかかわらず、業界特有の法令や通達を知らなかったために、過大な税金を支払うことになってしまうこともあります。
税理士が、あらゆる業種に関してすべての法令や通達を把握しておくことは非常に困難ですので、あらかじめ、同業者の方がお願いされている税理士を聞いてみたり、相談する際にご自身の業種の顧問先が他にもあるかなどといったことを確認されることをおすすめします。
4 どこまで依頼できるかを確認する
税理士の中には、領収書や通帳を送りさえすればすべて記帳や帳簿の作成、申告書の作成まで行ってくれるところもあれば、会計ソフトを導入しており、一定程度、依頼者が入力することを求められるところもあります。
ご依頼される方の月間、年間の仕訳数によっても変わってきますが、どこまでを依頼することができるのか、それによって顧問料も変わるのが一般的ですので、その点もご相談の際にご確認されることをおすすめします。
税理士を紹介してもらう際のメリットと注意点
1 どのように税理士を見つけるか

税金に関することを税理士に相談したい、具体的に税務業務を税理士に依頼したいという場合、税理士を探す方法はいくつかあります。
具体的には、自宅の近くの税理士事務所の看板を頼りに探してみる、インターネットで調べてみる、すでに知り合いの税理士に追加で相談や依頼をする、税理士紹介会社を利用する、知人に紹介してもらう、といった方法が考えられます。
ここでは、知人に税理士を紹介してもらう方法のメリットや注意点について、説明していきます。
2 税理士を紹介してもらうという方法のメリット
すでにその税理士に依頼している知人が身近にいる場合には、その知人が具体的にその税理士に相談をしたうえで分かった、税理士としての能力や人となりを聞くことができます。
そのため、ネットで探すよりも信頼できる税理士に出会える可能性が高くなります。
また、費用という面でも、すでにある程度知人が料金体系を知っているため、その知人と似たようなことを依頼するつもりであれば、税理士費用を推測することができ、安心です。
3 税理士を紹介してもらう際の注意点
信頼できる税理士であることも重要ですが、それは、頼もうとしている税務分野について、能力があることが前提です。
医者に外科医や内科医と専門分野が決まっているように、税理士も得意分野があります。
そのため、依頼しようとしている分野に詳しいかどうかを事前に確認することが大切です。
例えば、相続税に関する相談であれば、法人税や所得税を得意としている税理士に頼むよりは、相続税を得意としている税理士に頼んだ方がよいといえます。
特に、知人とは異なる内容について依頼するつもりである場合は、ご自身が相談したい分野については得意としていない可能性もありますので、事前に確認することが重要です。
最近は最初の相談に無料で対応してくれるところも増えていますので、まずは実際に相談してみることをおすすめします。
税理士に相談すべき場合
1 税理士の仕事内容

税理士と聞くと、大きな会社の経営者や、多額の個人資産を保有している資産家が相談し、依頼をする専門家というイメージを思い浮かべる方が多いです。
しかし、税金は日常生活に深く関わっており、ほぼすべての方に関係する事柄です。
税理士とはあまり縁のないサラリーマンであっても、毎月所得税を源泉徴収され、年末調整という所得税の計算が毎年行われています。
ふるさと納税を利用されている方や、医療費控除を受けたい方は、確定申告を行う必要がありますので、毎年申告を行っている方もいらっしゃるかと思います。
ご自分の関わる税金や、それに関する手続きについて、心配なことやご不安なことがありましたら、税理士にご相談いただくのがよいかと思われます。
2 個人の方が税理士に相談すべき場合の例
一つの法人で働いているだけの給与所得者であれば、原則として、確定申告は必要ありません。
勤務先で年末調整をすることによって、その年の所得税の計算がすべて行われるからです。
しかし、最近は、給与所得者でも副業をする方が増えてきています。
フリマサイトで反復継続して売買をしていたり、アフィリエイトで収入があれば、収入がある一定金額を越えた場合に確定申告をする必要があります。
副業の種類によって得られる所得は異なり、どの所得であるかによって確定申告の仕方も異なります。
どの所得に該当するかの判断やその申告方法は、税金の専門知識がないと難しいこともありますので、給与所得者の方が副業で確定申告をする場合は、税理士に相談すべきだといえます。
なお、副業をせず、一つの法人で働いているだけの給与所得者の方の場合でも、所得金額が2000万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
3 法人の方が税理士に相談すべき場合の例
法人の決算では、貸借対照表や損益計算書等の決算書を作るだけでなく、毎月の収支の確認、キャッシュフローの状況、経営の状況を確認したり、税理士に改善策を提案してもらうことが必要になります。
法人が大きくなればなるほど、会社の財務状況やキャッシュの状況が把握しづらくなりますので、黒字のはずなのにキャッシュがない、キャッシュは多いけれどもなかなか黒字にならないなど、経理業務の専門家である税理士に相談すべき場面が増えるかと思われます。
4 税務調査はできるだけお早めにご相談ください
中には、税務調査が行われることになった方もいらっしゃるかと思います。
税務調査では、帳簿、領収書、契約書、様々な書類について、税務署から事細かにチェックを受けることになります。
当然、税務署としては、本当は売上が多く、経費が少なめで税金の額はもっと多額なはずだと主張します。
このような税務署に対しては、税法に対する知識、理解がなければ、税務署の主張に反論することは難しく、本当であれば経費として損金処理できたはずの支出が損金として認められず、税金が高額になってしまうこともあり得ます。
そのため、税理士の立会いがあるか否かで、税務調査の結果に大きな影響を及ぼすこともあります。
税務調査が行われることになった場合は、顧問税理士がいれば顧問税理士に、いなければ税務調査だけでも対応してくれる税理士を探し出し、できる限り早く相談をすることが必要です。
税理士には得意分野がある
1 税理士の仕事

税金は法人が事業を行う場合にのみ関係してくるものではなく、個人が日常生活をする上でも密接にかかわってくる事柄です。
税理士の仕事は、法人や個人に対して、法人税・所得税・相続税等の税金に関するアドバイスをすること、申告書を作成することです。
具体的には、納税者の代わりに税務署とやり取りをする税務代理、各種税務書類の作成、税金に関する相談や税額のシミュレーション、e-TaXの代理送信、会計業務というように、その業務内容は多岐にわたります。
2 税理士の得意分野
また、税金といっても分野は幅広く、法人税、所得税に詳しい税理士もいれば、相続税、贈与税に詳しい税理士もいます。
税理士であれば、全税目について、税理士業務を行うことができるのですが、一般の方が想像する以上に得意な分野と不得意な分野がはっきり分かれています。
依頼した案件が、その税理士の得意分野ではなかった場合、その分野に関する詳しい知識、経験が不足して、処理が遅くなりがちであったり、ひどければ不適切な処理となってしまい、本来よりも多額の税金を納めなければならなくなってしまったりします。
3 税理士になるルートの影響
なぜ、税理士には、得意な分野と不得意な分野があるのでしょうか。
その背景には、税理士資格を得るためには複数のルートがあるという事情や、案件の分野の特性があります。
選択したルートによって、身につく知識、経験は多様であり、その後の得意分野にも影響が及ぶことがあります。
ほとんどの税理士は、①税務署に一定期間勤務すること、又は、②税理士試験に合格することにより、税理士資格を取得しています。
① 税務署に一定期間勤務して税理士になるルート
税務署に一定期間勤務した後に税理士になった人は、税理士全体の半数を占めます。
税務署に長期間勤めた税理士であれば、経験豊富で、どんな税目にも対応できそうだというイメージを抱くかもしれません。
しかし、実際には、税務署の職員は、特定の税目を担当し、その税目について退職するまで経験を積んでいきます。
その場合、担当していた税目については、知識、経験ともに豊富な税理士と言えますが、担当してこなかった税目については、詳しいことはわからないといったことが十分にありえます。
また、税務署の職員は、ほとんどが所得税、法人税等を担当しており、相続税を担当する職員は比較的人数が少ないため、このルートでは相続税を得意とする税理士は少ないと言えます。
② 税理士試験に合格して税理士になるルート
次に多いのは、税理士試験に合格して資格をとった税理士です。
税理士試験は、科目を選択して受験することができます。
具体的には、税法科目については、所得税、法人税、相続税、消費税、酒税、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税の9科目から、3科目を選択して受験することになっています。
なお、所得税、法人税については、そのうちの1科目を必ず受験する必要があります。
その他の科目は自由に選択することができます。
また、大学院を卒業することで、一部の試験科目が免除されることもあります。
この場合、選択した科目については詳しくはなりますが、選択しなかった科目については、必ずしもそうではありません。
・案件の分野の特性
特に、主に顧問業務を行っている税理士は、所得税・法人税・消費税については普段から慣れていますが、相続税・贈与税を取り扱うことはあまりありません。
これは、所得税・法人税・消費税が日常的に生じる月次業務であることに対し、相続税・贈与税は人が亡くなるといった偶然の事情によってしか発生しないからです。
相続税・贈与税は、偶然の事情によってしか発生しないにもかかわらず、非上場株式の評価や不動産の評価が必要となりますし、遺産分割、法定相続分や遺留分などの民法の相続分野に関する理解も必要となるため、難易度は高い分野であるといえます。
4 税金に関するご相談は当法人へ
上記のように、税理士には得意分野がありますので、税理士を選ぶ際には、注意が必要です。
当法人では、各税理士が所得税・法人税・消費税チーム、相続税・贈与税チームなどに分かれて対応させて頂いており、それによって特定の分野に集中的に取り組むことで経験数を高め、各税理士が得意分野を担当する体制を作っています。
どの税金に関するご相談でも、お気軽にご相談ください。
税理士に相談する際に大切なこと
1 税務相談をお考えの方へ

税理士の主な業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談です。
しかし、これらについて相談をするといっても、どういった税理士に相談すべきか、よく分からない方もいらっしゃると思います。
そういった方のために、ここでは税理士に税務相談をする際に大切なポイントを説明していきます。
2 相談する税理士を選ぶ際に大切なポイント
⑴ 税理士との相性
当たり前ですが、相談しやすいことが大切です。
人間的な相性もありますし、気軽に相談できるかどうか、丁寧に説明してくれるかどうかを見極めることが大切です。
⑵ 便利な場所に事務所があること
税理士にすぐに相談できる環境が大切です。
相談しようと思えば気軽に行くことのできる事務所かどうかも、見ておくことをおすすめします。
税務においては、緊急で税理士と打ち合わせをする必要があることもあるため、事務所への行きやすさというのも大切なポイントです。
駅近くにある事務所であれば、仕事や買い物のついでに相談に行きやすいなど、お客様の利便性を考えている税理士事務所であることが多いです。
⑶ 相談する税目・業種についての経験
税理士だからといって、すべての税目・すべての業界に精通しているわけではありません。
相続税を得意としている税理士、法人税を得意としている税理士、法人税の中の特定の業界に精通している税理士など、様々な税理士がいますので、自分が必要としている分野が得意な税理士であるかどうかをご確認ください。
⑷ 年齢
年齢が高い税理士であるほど頼りがいがあると考えがちです。
確かにその傾向がないとはいいきれませんが、年配であるほど実際の実務で必要となるITスキルが不十分な場合もあります。
また、レスポンスが遅い場合もあります。
例外もありますので、自分の相談したい内容において、必要なスキルを備えている税理士を探すことをおすすめします。
⑸ 料金体系
報酬体系を確認することはとても大切です。
どのような仕事をどこまで頼めば、税理士報酬がいくらになるのか、はっきり分かるように提示されているかをご確認ください。
基本的に、料金体系がしっかり決まっているところは、その他の面においても体制が整っていることが多い印象です。
3 税務相談の時期
税理士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
例えば、まだ起業をされていないのであれば、起業前に相談すれば、税務面から創業のサポートを受けることが可能です。
事前に税理士のサポートを受けることで、早期の解決や適切な対処が期待できるため、何か税務面で問題が生じた時も、できる限り早く相談することをおすすめします。
顧問税理士とは
1 顧問税理士とはどのようなものか

税理士と年間を通じて継続した税務サービスを契約することを税務顧問契約といい、契約をしている税理士を顧問税理士といいます。
顧問税理士は、定期的に経理状況を把握して、年間を通して税務処理を行い、税務署から連絡があれば、納税者の代わりに税務署と折衝したりします。
また、優遇税制の情報等を随時、納税者に知らせることもあり、税務に関して全面的にサポートを受けられます。
2 顧問税理士とスポット契約
税理士に依頼する場合は、定期的・継続的にサポートを受けられる顧問契約ではなく、申告だけを依頼するという、特定の業務のみを依頼できるスポットの契約をすることもできます。
ただ、確定申告書等の税務書類を作成し税務署に申告することだけでなく、税務面において定期的・継続的なサポートが必要な方にとっては、顧問契約を結ぶ方がメリットは大きいといえます。
3 顧問税理士と経理業務
顧問税理士は、経理業務について指導することが多く、契約の内容によっては経理代行を任せることも可能です。
経理業務や記帳業務をおろそかにしていると、税務調査が入ってしまったときに対応が難しくなり、効果的な対応ができないこともあります。
また、補助金の申請では、ほとんどの場合、前提として正確適正な経理業務、記帳業務を行っていることが必要となります。
そこで、普段から顧問税理士に経理指導や経理代行を依頼していれば、税務調査や補助金の申請等を行うときに、よりスムーズに対応することができます。
4 顧問税理士と経営
経営者の業務は多岐にわたり、非常に多忙です。
また、経営者の一番の仕事は、事業の売上を伸ばすことです。
にもかかわらず、重要とはいえ、経理業務に時間をかけていては、本業に注力することができません。
顧問税理士がいれば、煩雑な経理業務を任せたり、経営の相談をしたりすることができます。
このように、業務を依頼したり相談したりすることが常にできるというのも、顧問税理士がいる最大のメリットともいえます。
これにより経営者は本業に専念し続けることができますので、事業の売上を伸ばしていけることにつながります。
税理士に依頼した場合の料金
1 税理士の料金の定められ方

税理士の料金は、平成14年3月までは税理士法で規定されていましたが、その後、税理士法が改正され、税理士会の報酬規程が廃止されました。
結果、各税理士事務所、税理士法人が、それぞれ独自に決めた料金表を使用するようになりました。
報酬額自体も自由ですし、報酬体系も自由となっています。
そのため、セット料金を特徴とした報酬体系をとっているところもあれば、基本料金をできる限り抑えて、付随業務についてオプション料金を取るところもあります。
例えば、月額の顧問料に、年末調整の費用を含める場合もあれば、月額の顧問料を低額にする代わりに、年末調整の費用等をオプション料金として加算して請求する場合もあります。
そのため、税理士の料金については、ご自分が依頼しようとしている税理士に対し、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
2 税理士の料金の内訳
税理士の料金の内訳としては、顧問料、記帳代行料、決算料(確定申告代行、消費税申告代行)等があります。
また、年末調整や各種書類の作成といった税理士業務に関する費用が別途オプション料金とされている場合もあれば、顧問料に含まれている場合もあります。
3 税理士報酬の決まり方
通常の場合、税理士報酬は事業の売上の金額や作業量で決まります。
売り上げが大きければ大きいほど、作業量が多くなる傾向にありますし、税金の額も大きくなる傾向になるためです。
作業量は領収書の枚数や仕訳の数等を基準にして、その量が多ければ多いほど税理士報酬が高くなる傾向にあります。
そのため、税理士に依頼をする際には、「どこまで依頼するのか」を明確に決めておくことが大切です。
どこまで依頼するかというのは、例えば、申告のみ頼むのか、記帳代行まで依頼するのか、そのほかのことも頼むのかといったことです。
また、顧問料にどこまでが含まれて、どこからがオプションとして別途費用がかかるのかを、税理士に確認しておくようにしてください。
税理士にこれから依頼しようとしている方は、上記の点を意識しながら、納得できるまで確認をしておくことをおすすめします。
税理士との関係は、長く続くことが多いので、最初に、できる限り明確にしておくことが重要です。
各専門家が協力できることの強み
1 税理士と他分野の専門家が協力

税理士は、相談内容やお客様の状況によっては、他分野の専門家と協力する必要が出てくることも多いです。
そのような場合に、これまで他分野の専門家と協力したことのない税理士よりも、何度も他分野の専門家と協力し連携に慣れている税理士の方が、問題をスムーズに解決することができます。
ここでは、税理士と弁護士が連携する場面を例にして説明していきたいと思います。
2 税理士と弁護士の連携
⑴ 税金のことを考慮しながら協議等を進められる
弁護士は、交渉、訴訟等には慣れていても、税金面にまで詳しい場合は少ないといえます。
税理士と連携することで、例えば遺産分割の協議の段階であれば、分割の方法によって特例の適用を受け、税金を軽減できるということを、税理士からアドバイスすることができます。
このように、依頼者にメリットのあるアドバイスができるほか、全体の税金を抑え、相続人全員が利益を受けるようにできる場合もあります。
⑵ 資料をスムーズに集められる
また、交渉、訴訟等の結果、相続した不動産を売却すれば、譲渡所得税を確定申告する必要があります。
このような場合に、弁護士と税理士が連携できていれば、確定申告に必要な資料がすぐに集まり、スムーズに申告することができる場合が多いです。
このように、弁護士と連携のできる税理士に依頼した場合のメリットは多いため、ご相談の際にはそういった税理士を選ばれることをおすすめします。
税理士に相談した方がよい人
1 個人事業主・会社経営者の方

事業を営まれている方の場合は、正しく経費を計上するため、税理士に相談されることをお勧めします。
思い違い等により、本来経費に計上できないものを計上しているなどといったことがあった場合、税務調査によって追徴課税をされるだけでなく、過少申告加算税等のペナルティを課せられることがあります。
インターネットから得られる情報の中には、経費計上の是非について、誤った情報も散見されますので、違法な脱税方法ではなく、法で認められた方法で節税対策を行うためにも、税理士にご相談ください。
2 給与所得で医療費控除を行いたい方
医療費控除を受けたい方は、確定申告が必要となりますので、税理士に相談されることをお勧めします。
医療費控除では、例えば、予防接種は控除対象に含まれないといった、知識がある方でなければ誤って控除対象としてしまうようなものもありますし、子どもの鼻吸い器のような、一見すると医療費控除の適用対象外とも思える物が適用対象であったりします。
どのようなものが医療費控除の適用対象となるかは、判断が難しい場合もありますので、税理士に相談されることをお勧めします。
3 還付が受けられる方
源泉徴収をされている方で、確定申告をすれば還付金を受け取ることができる方は、確定申告をすべきですので、税理士に相談されることをお勧めします。
4 資産を譲渡した方
資産を譲渡した場合、資産が値上がりしていると譲渡した側には所得税が課されます。
資産を受け取った側は、資産に対して適正な対価を支払っている場合は特に課税問題は生じませんが、無償で譲渡をされた場合や、著しく低額な譲渡の場合は、贈与税が課税されることがあります。
また、上記は個人対個人の場合を想定していますが、個人から法人への譲渡、法人から個人への譲渡、法人間での譲渡の場合に、それぞれかかる税金の種類や控除対象額、税金の額が異なりますので、税理士に相談されることをお勧めします。
5 相続を受けた方
相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数)以下であれば、相続税はかかりません。
しかし、相続財産に不動産が含まれる場合や非上場株式が含まれる場合など、資産の評価が必要となる場合は、相続財産が基礎控除額以下であるかどうかの判断に知識が必要となりますので、税理士に相談されることをお勧めします。
税理士に相談してから申告までにかかる時間
1 所得税の申告の場合

所得税の確定申告と一言でいっても、所得の種類、金額、複雑さは人によって異なります。
例えば、収入が給与や年金のみで事業所得がない場合には、資料収集から申告書作成及び申告までにかかる時間は比較的短くすみます。
こういったケースにおいては、給料又は年金の源泉徴収票、社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、ふるさと納税寄附金控除に関する証明書、医療費控除にかかる領収書、住宅ローン控除のための住宅借入金等特別控除申告書、といった書類を収集し、まとめて税理士に渡せば、税理士が申告書を作成してくれます。
こうした申告書の作成にかかる期間としては、通常ですと1~3週間程度かかるとみておいたほうがいいでしょう。
これに対し、事業をしている場合で、顧問税理士がおらず、年に1回だけ税理士に確定申告を任せるという方の場合は、もっと時間がかかります。
この場合、税理士が帳簿をチェックしたり、まとめたりすることから始めなければならないためです。
さらに、帳簿を作成していない場合には、請求書、領収書、通帳等を整理したうえで、帳簿の作成から始めないといけませんので、1か月から3か月程度の時間がかかることもあります。
そのため、この場合には特に早めに税理士に相談することをおすすめします。
2 贈与税の申告の場合
贈与税を減額するための特例を使わない場合には、たいてい1~3週間あれば、申告書を作成することができます。
贈与税を減額するための特例を使用する場合は、一定の書類を収集する必要があるため、そこに時間がかかることもあります。
また、贈与税は、相続税とも密接な関係にあるので、贈与の計画を立てたり、そもそも贈与するかどうかを検討したりすることに、時間がかかることも多いです。
特例により贈与税を減額したいという方の場合には、そもそも特例を使用できる要件を満たすかどうか、贈与する前から税理士に相談しておくことをおすすめします。
3 相続税の申告の場合
相続税の申告では、大量の書類を収集する必要があり、収集が終わればそれらを整理して申告書を作成することになります。
また、税額軽減の特例を適用するために、申告期限までに分割協議を行う必要があります。
このように、申告にあたって行わなければいけないことが多いため、相続税の申告書の作成にかかる時間としては、1~3か月ほどをみておくことをおすすめします。
また、相続人が被相続人の財産を全く知らない場合は、そもそも、財産調査をする必要あがり、そこにも時間がかかってしまいます。
そのため、生前にある程度財産を整理しておくこともおすすめします。
4 税理士に相談するタイミング
このように、税理士が申告書を作成するには、ある程度時間がかかりますし、そもそも申告前に検討や資料の収集が必要なこともあります。
そのため、税理士にはできる限り早いタイミングで相談をしておく必要があるといえます。
税理士を選ぶ際のポイント
1 税理士を探すときのポイント

税理士に依頼をしたい時、どのようなポイントに気を付けて探せばいいのでしょうか。
個人事業や法人の経営者にとって、事業を行うことで発生するお金の流れを適切に税務処理するということは非常に大切なことであり、それを担う役割である税理士は慎重に選ぶべきです。
良い税理士に依頼することができれば、節税だけでなく、経営に関するアドバイザーとしてビジネスを成功に導いてくれます。
そのため、どういった税理士に依頼すべきか、良い税理士の特徴をこちらで説明していきたいと思います。
2 相性が良い税理士
税理士との人間的な相性が悪ければ、どれだけ優れた思考と知識を持っている税理士だとしても、十分なコミュニケーションが取れず、納得のいく相談をすることができません。
税理士が優れた相談役となるか、ただの書類作成をするだけの存在となるかは、最終的には税理士との相性次第です。
税理士に依頼をする際は、実際に話をして、お悩みのことを気軽に相談できるかどうか、相性が良いと感じられるか等といった観点から選ばれることをおすすめいたします。
3 日々の勉強を欠かさない税理士
税制は毎年改正され、知らなければ税金の面で大きな損をする改正もたくさんあります。
毎年変わっていく税制を把握し、経営者の方に適切な提案をできるようにするためには、日々の勉強が欠かせません。
しかし、日々の業務に追われ、勉強がおろそかになっている税理士も少なくありません。
税理士には、義務研修が年間36時間課されており、各税理士が最低限の義務研修の受講時間を達成したかどうかは、日本税理士連合会のサイトで確認することができます。
税理士をお探しになる際には、そちらも一度確認してみることをおすすめします。
また、若い税理士のほうが最近の制度には詳しいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
税理士の平均年齢は60代ですが、年齢の高い税理士だからといって毎年の改正に対応できていないとも限りませんし、長年税理士をやっている分、豊富な知識経験を有している方も多いです。
若い税理士にも年配の税理士にも、それぞれにいいところと悪いところがあります。
そのため、どちらの年齢層の税理士も所属していて、お互いに切磋琢磨しているような税理士事務所が理想といえます。
4 レスポンスが早く様々なことに柔軟に対応してくれる税理士
税金は期限を守ることが非常に大切です。
最たる例は、確定申告期限ですが、青色申告の承認を受けるための期限、消費税の計算方式で簡易課税を選択するための期限など、税額に大きく関わってくる期限が多数あります。
そういった期限があるため、税理士のレスポンスが早いことはとても大切です。
また、税理士の中には税金の計算に注力し、それ以外のことには関わらず、アドバイスをしない税理士もいます。
個人経営者の方であれば、経営相談、節税アドバイス等、柔軟に色々なことに対応してくれる税理士がおすすめです。
経営の中で税務以外の問題が生じることもあるかと思いますが、それらについて、直接解決手段が示せないとしても、お客様の問題が解決できるように、信頼できる弁護士や司法書士を紹介してくれるような、顔の広い税理士もおすすめです。
当法人へのご依頼の流れ
1 まずはお気軽にお電話ください

当法人のフリーダイヤルにお電話いただき、どういった税金(所得税、法人税、相続税など)のご相談かを受付へお伝えください。
フリーダイヤルは、平日の9時から21時、土日祝日の9時から18時までつながります。
受付の者が、ご相談にあたって必要となる事項をお聞きし、税理士に相談するまでの流れについてご案内させていただきます。
フリーダイヤルだけではなく、メールフォームからもご相談のお問合せが可能です。
2 税理士との税務相談
税理士との税務相談は、事務所までお越しいただくか、もしくはお電話・テレビ電話でご相談いただくかをお選びいただけます。
電話・テレビ電話相談の場合は、事前にご相談方法についてご案内いたしますので、ご安心ください。
税理士が、事業の内容、売上規模、従業員の人数等をお聞きしながら、税金に関するご相談に乗らせていただきます。
お悩みの内容が、税理士として関与させていただけるものであれば、こちらで対応させていただく業務の内容や顧問料等についてお見積もりをさせていただきます。
3 ご依頼
対応させていただく業務の内容やお見積額に問題がなければ、契約書に署名押印をしていただきます。
契約にあたり、ご不明点等があれば、ご納得いただけるまで丁寧に税理士がご説明をさせていただきますので、お気軽にご質問ください。
税理士の探し方
1 税理士を探す方法は様々

街中で目にした事務所の看板を目安に事務所を探される方もいれば、インターネットで検索される方、新聞やチラシ等の広告の情報を利用される方など、税理士の探し方は人それぞれです。
相談したい内容とあわせて、ご自身のご都合に適した方法で探されることをおすすめします。
2 知人から紹介してもらう
どの税理士に相談すればよいのか分からず困ってしまう方も多いかと思います。
そのような場合は、お知り合いの方に税理士を紹介してもらうという方法もあります。
この方法の場合、そのお知り合いから税理士について話を聞くことができますし、ある程度信頼できる税理士である可能性が高いです。
ですが、税務分野は多岐に渡るため、税理士によって得意としている分野が異なります。
そのため、ご相談の際は、紹介してもらう税理士がお悩みの分野を得意としているかどうかを見極めることが重要です。
また、相談しやすいか否かという点も重要になります。
相性の良し悪しは人それぞれですので、お知り合いの紹介だからといって必ずしもご自分にも合っているとは限りません。
人柄や相性、信用できる人物なのかといった点をご自身でしっかりと見極めることが大切です。
3 インターネットで探す
インターネットは知りたい情報を簡単に入手することができる一方で、その情報が信用できるものかを判断することは簡単ではありません。
情報の信頼性を見定める手段として、ポータルサイトを見ること、その中から気になった税理士事務所のホームページを見ることが挙げられます。
⑴ ポータルサイトを見る
ポータルサイトの利点として、たくさんの事務所が掲載されているため、一度に閲覧することができるという点が挙げられます。
多くの情報が掲載されているため、その中から自分に適した事務所を見極めることが重要となります。
ですが、事務所ごとの情報が少なく、似たようなことが書かれていることもあるため、判断が難しいかもしれません。
⑵ 事務所のホームページを見る
どこに相談するかを判断するためには、その事務所に関する詳しい情報を知る必要があります。
各事務所のホームページを見ると、事務所の特徴、強み、力を入れている分野が分かります。
ポータルサイトよりも情報量が多いため、自分の求めているサービスを提供してくれるかどうかを判断する際に、役に立つ情報を得ることができるかと思います。
4 お悩みの方は当法人にご相談ください
当法人は、税に関する様々なサービスを提供しています。
そして、ご相談の際に丁寧にお客様のお悩みをお伺いし、一人一人に適したサポートを提供できるように努めています。
当サイトでも、当法人のことや税金に関する情報などを掲載しておりますので、参考にご覧いただければと思います。
税理士をお探しの方は、一度当法人までお気軽にご相談ください。
当法人の特徴
1 より質の高いサービスを提供

税務に関するお悩みの中には、会計や税金の知識・経験に加えて、他の専門知識もあった方がより良い対応ができるものがあります。
当法人では、グループ内の他の専門家と密に連携できるため、税務に加え法律問題や労務問題が関係してくるようなご相談においても柔軟な対応が可能です。
お客様のお悩みに応じて、税務を含めた幅広く適切なサポートをさせていただきます。
より質の高いサービスを提供できる環境を整えておりますので、お悩みの方はどうぞ一度ご相談ください。
2 様々なご相談に対応可能
当法人では、事業者の方だけでなく、個人の方からの税に関するご相談もお受けしており、相続税申告や確定申告など、幅広いご相談に対応しております。
よくあることですが、相続において、税金の問題と法律の問題が同時に起こった場合、それぞれ別の事務所を探す必要はありません。
当法人では、必要に応じて他の専門家と円滑に連携できるようにしているためです。
スムーズで柔軟な対応が可能ですので、このような複数の問題を抱えている方でも、まずはお気軽に当法人までご連絡ください。
3 ご利用いただきやすい環境
多くの方にお問い合わせいただきやすいように、また、お仕事が終わった後にお電話していただくこともできるように、当法人では平日21時までつながるフリーダイヤルを設置しています。
土日祝日も18時までお電話がつながるようになっておりますので、お忙しく平日には電話をかける時間がないという方もご連絡いただきやすいかと思います。
また、当法人はご紹介がない方でも全く問題ありませんので、初めての方も安心してご連絡ください。
当法人に税務相談する際に用意していただくもの
1 事業の概要をまとめたメモ

税理士に初めて相談する際、税理士はまだ相談者の方のことを詳しくは把握していません。
そのため、相談者の方がどのような事業をしているのか、例えば飲食業なのか、建設業なのか、接骨院を経営しているのかといったことを知る必要があります。
業種によって気を付けるポイントが異なりますので、まずは、顧客は誰なのか、何を提供しているのかといった、事業内容に関する情報をまとめておいていただくと、よりスムーズに相談をすることができます。
また、事業規模や従業員数も重要となってきます。
事業規模が大きければ大きいほど税務が複雑になる傾向がありますし、従業員の人数が分かれば年末調整等の人件費に関わる税務処理の作業量の見当がつきます。
2 税理士に渡す資料
事業の概要だけでなく、事業規模の把握のため日々の売上と経費の資料を税理士に見せる必要があります。
請求書、領収書の他、帳簿を作成しているのであればそちらも見せていただくと、税務相談の時間を有意義にご利用いただくことができます。
帳簿があれば、税理士としても事業規模や経理の複雑さを把握しやすくなるためです。
その他にも、源泉徴収票、控除証明書類、医療費の領収書、住宅ローンに関する書類などの収入及び所得控除に関係する資料は、まとめてお持ちいただくとよいです。
また、過去に確定申告をされている方は、過去1年分以上の確定申告書の控えをお持ちください。
可能であれば、過去3年分程度の確定申告書の控えがあると、より正確に事業内容・事業規模を把握することができます。
3 まずはお気軽にご相談ください
上記のものがあれば、スムーズに相談を進められますが、これらが無ければ相談できないというわけではありませんので、ご安心ください。
帳簿を作成していない、そもそもどういった書類を保管すればいいのか分からないという方もいらっしゃると思いますが、その場合でも税務について税理士にご相談いただけますし、これらの点についてアドバイスさせていただくことも可能です。
また、相談内容によって必要な書類が異なることもありますので、基本的には税理士に直接問い合わせて、何が必要か確認することをおすすめします。
当法人にお問い合わせいただければ、用意していただく書類について丁寧に分かりやすく説明させていただきますので、まずは、お気軽にご相談ください。
税理士に依頼すべきタイミング
1 個人事業主の方の場合

⑴ ご自分で確定申告をすることが不安なとき
税理士に顧問を依頼する一つの目安となるのは、収支内訳書や現金出納帳などの書類を作成することが難しく、確定申告をすることが不安な場合です。
個人事業主が保管しなければならない帳面や書類は法律で決められていますが、単に領収書を保管しておけばよいというわけではありません。
特に、青色申告を行い、65万円の特別控除を受けたい場合には、作成しなければならない書類や手続きがより複雑になります。
ご自分でこれらの書類を作成することが難しいと判断されるようでしたら、税理士にご依頼されることをおすすめします。
⑵ 法人成りをするとき
法人成りをするときも、税理士に顧問を依頼するタイミングの目安になります。
法人化をすると、所得税ではなく、法人税の計算・申告をする必要があります。
法人税の申告では、法人税申告書、決算書、勘定科目内訳表、事業概況書を提出する必要があります。
また、法人設立に際しては、税理士に顧問を依頼することにより、会社設立手続きのサポートを受けることができます。
例えば、会社設立をすると税金関係の書類を税務署や自治体に各種届出をする必要がありますし、役員報酬額を決める必要があるなど、所得税の確定申告とは異なるところがたくさんありますが、税理士にそれらを任せたり必要な手続きについてアドバイスを受けたりすることができます。
そのため、法人成りのタイミングが、顧問税理士を依頼する一つの目安といえます。
⑶ 売上が1000万円を超えたときやインボイスの登録事業者となるとき
売上が1000万円を超えたときやインボイスの登録事業者となるときも、税理士に顧問を依頼すべきタイミングの一つといえます。
これらの場合は、消費税の申告が必要となることがあり、ご自身でこれらの申告書を作成することが難しいとされているためです。
2 すでに法人を設立している方の場合
ご自身で法人の申告をされている場合、顧問税理士を頼むタイミングの目安は、事業の売上が1000万円を超えたときです。
事業の売上が1000万円を超えた場合、その事業年度の2年後から消費税の納税義務者となります。
そうなると、税務関連の業務が増大します。
具体的には、消費税に関する申告書を作成しなければならないため、普段の会計処理が複雑になり、非課税取引ではないか、税額控除が受けられるのではないかなど、気をつけるべきことが増えます。
また、こういった事業の売上が多くなったタイミングで、税理士に相談すると、節税に関してアドバイスを受けられることもあります。
なお、インボイスの登録事業者となった場合も、同様に消費税の申告が必要となりますので、税理士に相談すべきタイミングといえます。
3 これから法人を設立する・事業を開始する方の場合
まだ法人を設立されていない場合は、法人の設立に関する相談も含めて、顧問税理士を依頼することをおすすめします。
このタイミングで依頼をしておけば、最初から税理士によるアドバイスや支援を受けられるため、開業準備にかかった費用のうち、何が経費として処理できるかなどの経理処理、会計処理をスムーズに行うことができます。
また、個人事業を開始される予定の方も、事業を開始される前段階である事業計画書の作成の段階から相談されることをおすすめします。
融資を受けやすい事業計画書の作成について税理士からアドバイスをもらえますので、スムーズに事業を開始できる可能性があるためです。
自分で税務関係の業務をやってみたものの、思っていた以上に難しい又は経理処理を的確に行う時間的余裕がないという場合には、期の途中でも税理士に依頼することができます。
ただ、途中から頼まれた場合は、依頼前の帳簿の処理方法のチェックや修正のため、報酬が余計にかかってしまうなどの可能性もありますので、早めに相談されることをおすすめします。
なお、税理士への依頼は、時間の余裕をもって依頼することが大切です。
決算の直前に依頼をしようとすると割増料金がかかってしまったり、そもそも依頼を断られたりする可能性もあります。
4 税理士をお探しの方
これから税理士を探そうとされている方は、その税理士と信頼関係を構築できそうか、自分が相談しようとしている分野がその税理士の得意分野か等をご確認ください。
当法人には経験豊富な税理士が在籍しておりますし、必要に応じて他の士業とも連携できる環境を整えています。
税に関してご不安な点やお悩みがありましたら、当法人までお気軽にご相談ください。
確定申告について
1 確定申告と青色申告

個人事業者は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を毎年翌年の2月15にから3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
確定申告の原則的な方法は、白色申告といいます。
「白色申告」は、簡易帳簿をつければよく、複式簿記による帳簿の作成義務のある青色申告と比べると、比較的簡単に申告することができます。
他方、原則として複式簿記で帳簿をつける等、一定の要件を満たすことにより、税務署長の承認を前提として、税制上の優遇を受けられる申告方法を「青色申告」といいます。
税制上の優遇とは、具体的には、最大65万円の控除、赤字の最大3年間繰越ができる等の優遇があります。
青色申告という名前の由来は、元々、青色申告をする場合の紙の色が青色だったということからきているようです。
2 確定申告と青色申告承認申請書の提出期限
青色申告をするためには、一定の期間内に、所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
その一定の期間とは、原則として、青色申告をしたい年の3月15日までの期間です。
ただし、新規開業をした場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)には、業務を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告を行っていた事業者が亡くなり、相続人が事業を相続した場合も、相続開始を知った日から所定の日数までに書類を提出する必要があります。
具体的には、その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合は死亡の日から4か月以内、その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合はその年の12月31日まで、その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合にはその年の翌年の2月15日までに提出をするひつようがあります。
なお、提出期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合には、これらの翌日が期限となります。
3 青色申告を行うメリット(青色申告特別控除)
青色申告を行う一番のメリットと言われているのは、65万円の控除が受けられることです。
青色申告をして、65万円の特別控除を受けるための要件は、以下の3つです。
①不動産所得又は事業所得が生じる事業を行っていること
②事業に関する取引を複式簿記の方法に従い記帳していること
③その記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること
なお、不動産所得がある事業者で、事業規模に達しない納税者の場合には、残念ながら、10万円の控除しか受けられません。
4 青色申告特別控除の注意点
令和2年以降の確定申告においては、青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられています。
ただし、電子申告等を行うことによって、さらに10万円の控除を受けられます。
つまり、電子申告等をせず、紙で申告書を提出する事業者の場合、青色申告特別控除額が10万円少なくなってしまうということです。
そのため、これまで電子申告をしていなかった事業者の方も、今後は電子申告を行うことをおすすめします。
税のことでお悩みの方はご覧ください
お悩みの方のご参考になるように、様々な情報を掲載しています。こちらをご覧いただくとともに、当法人の税理士にご相談ください。