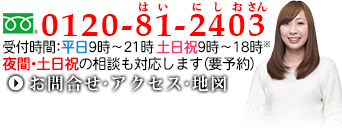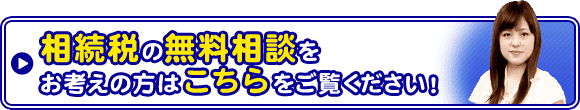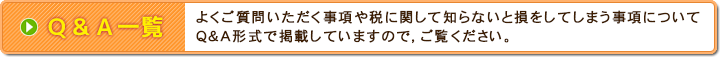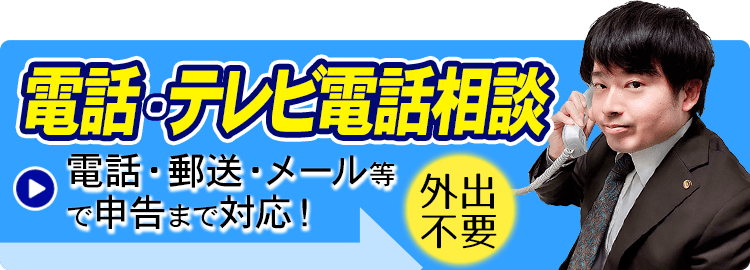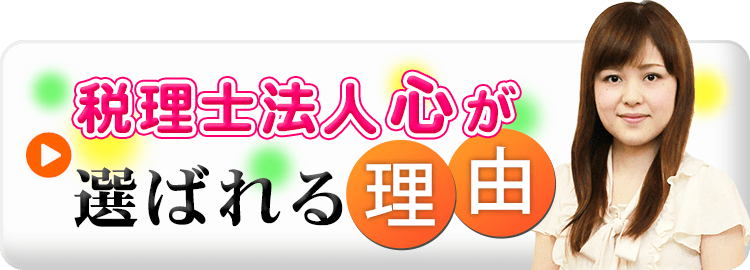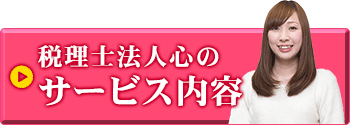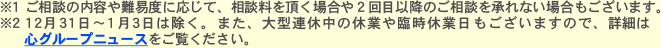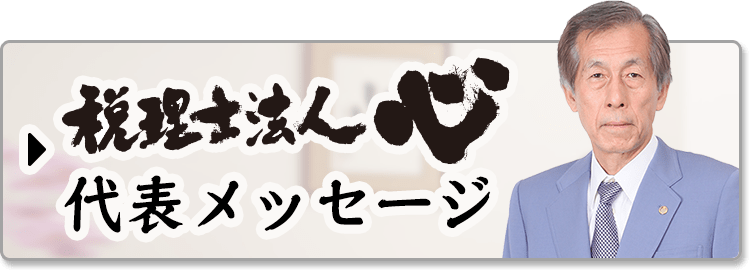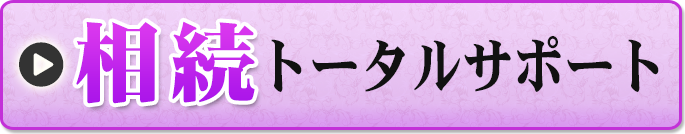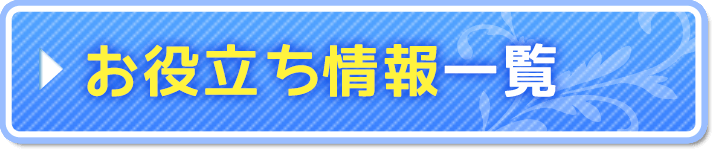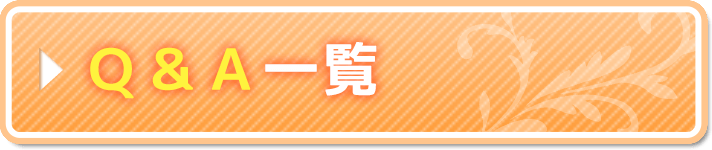相続税の対象となる財産
1 相続税の対象となる課税財産
相続人は、被相続人のすべての財産、権利、債務を引き継ぐことになります。
財産を引き継ぐと、金銭的に価値を見積もることのできる財産のすべてに対して相続税が課税されます。
具体的には、土地、建物、現金、預金、有価証券、貴金属、貸付金、著作権といったすべての財産が、相続税の課税対象となります。
「建物が古すぎると金銭的価値がないのではないか」と思われることもあるかもしれませんが、実際には建物の固定資産税評価額を相続税評価額とみなして、金銭的価値を見積もります。
参考リンク:国税庁・土地家屋の評価
したがって、ご自身では相続したものに金銭的価値がないと思っている場合であっても、実際には金銭的価値があり、相続税の対象となる財産を相続している場合がありますので、注意が必要です。
2 相続財産とみなし相続財産
死亡保険金は、保険契約に基づいて考えると受取人の財産であって、被相続人の財産ではありません。
遺贈や贈与にも該当しないため、民法に基づけば、遺産分割の対象となる相続財産ではないといえます。
しかし、実際は被相続人の財産から保険料が支出され、保険金が下りるのですから、相続税法上は、相続税の課税対象となる財産とされます。
このように、民法上は相続財産ではなく、遺産分割の対象にもならないものの、相続税が課税される財産のことをみなし相続財産といいます。
被相続人の死亡を原因として支払われる死亡退職金も、死亡保険金と同じようにみなし相続財産に該当します。
3 相続税と非課税財産
一方で、金銭的に価値があるものの、相続税が課税されない財産もあります。
墓地、墓石、仏壇、仏具等といった財産には、相続税がかかりません。
参考リンク:国税庁・相続税がかからない財産
また、死亡保険金や退職手当金の場合、500万円×法定相続人の人数で計算される金額までは、相続税はかからないと定められています。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡退職金
4 相続税と暦年贈与及び相続時精算課税制度を適用した贈与
基本的に、生前に被相続人から相続人へと贈与された財産は、被相続人の相続財産ではなくなります。
しかし、生前に贈与された財産であっても、そのすべてを非課税の相続財産とし、相続税の計算に含めなくてもよいというわけではありません。
贈与された時期によっては、さかのぼって相続税がかかる場合などがあるため、上記のような認識でいることで計算を誤ってしまい、税務署から申告内容について指摘を受けてしまうおそれがあります。