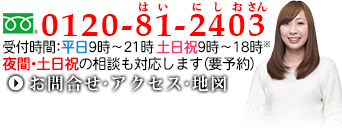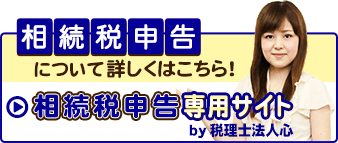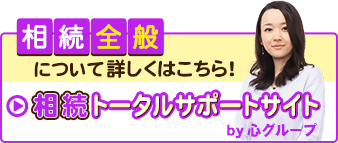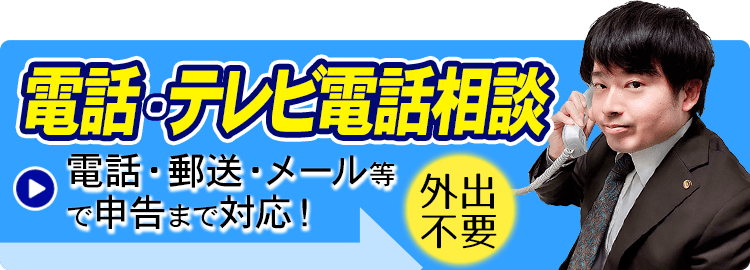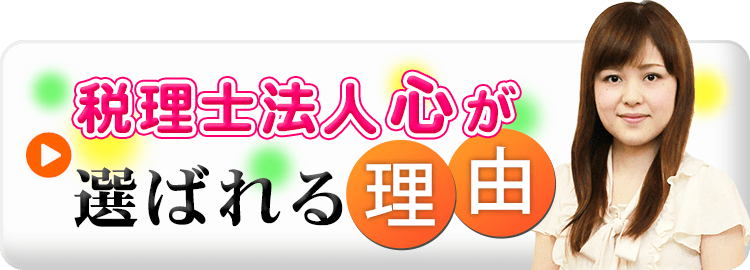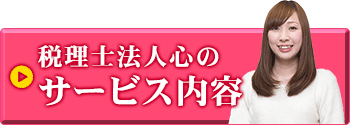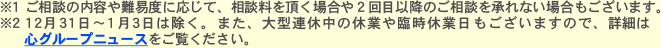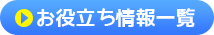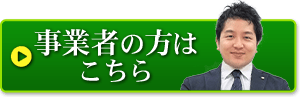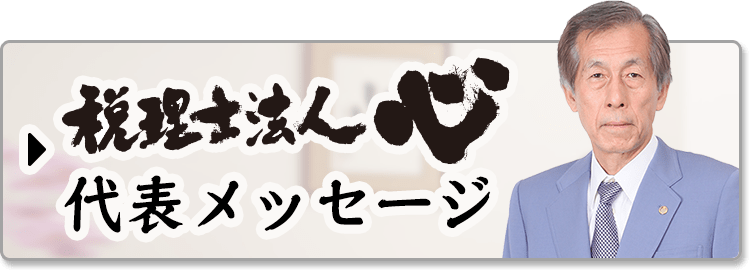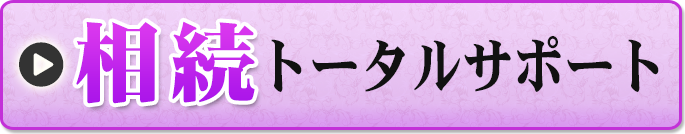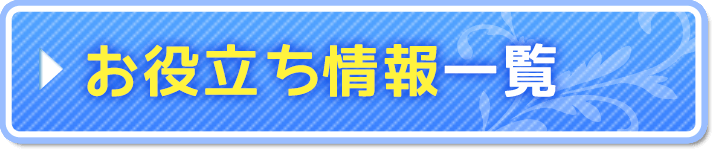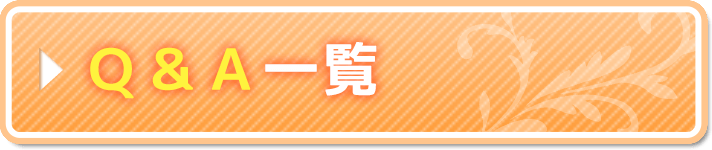相続税申告(相続発生後)

お客様に代わり相続税申告を代行いたします。
ご家族などが亡くなられた際に、財産を譲り受けた方に対し相続税がかかる場合があります。
相続税がかかるのは、相続財産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合です。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなられた日)の翌日から10ヶ月以内 に手続をしなければなりません。
- ご家族が亡くなられ、財産を譲り受けたが相続税の申告が必要なのか分からない方
- 相続税の申告をしたいがどうしてよいのか分からない方
- など
上記の方は、是非一度ご連絡ください。
税理士法人心では、お客様が相続される金額と基礎控除額を比較し、相続税が生じるかどうかを計算し、必要に応じて手続の代行も承ります。
- 当法人のサポート内容
-
- 相続税申告
- 相続税調査
当法人の事務所について
当法人は様々な地域に事務所を設けており、名古屋にも複数の事務所があります。各事務所の所在地など詳しい情報はこちらからご確認いただけます。
相続税の過剰な支払いにご注意ください
1 相続税を納める仕組み

相続税の申告では、税額算定の仕方によっては必要以上に税金を払い過ぎてしまうというケースがあります。
「払い過ぎることなんてあるのだろうか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
なぜ、このようなことが生じるかといいますと、相続税を納める仕組みが「申告納税方式」となっていることが原因だといえます。
申告納税方式とは、相続税の申告が必要だと判断した納税者が、自分で相続財産の把握とその評価をし、自らが申告書を作成して、相続税の税額を確定した上で、自分で納付書を作成し、納めることをいいます。
財産の把握・評価、相続税の計算まで、すべて自分自身で行わないといけないのですが、相続税の計算は複雑ですし、税負担を軽減するための各種特例や控除も用意されています。
これらを適切に行うことができないと、過大な相続税を納めることになってしまうのです。
以下で詳しくご説明いたします。
2 相続税の払い過ぎの原因
⑴ 土地は評価が難しい
相続税の払い過ぎは、土地の評価の間違いによって起こることが多いです。
土地が、現金や株式と比べて、評価が難しい財産といわれるのは、路線価という国税庁が毎年発表する指標による評価に加え、様々な減額要因があるからです。
この減額要因には、例えば以下のような点が挙げられます。
・土地が広すぎる
・土地の形がゆがんでいる
・近隣環境に問題がある
・道路との高低差がある
こういった減額要因が見過ごされ、適切に評価されていないと、本来あるべき金額より評価が高くなり、相続税もその分多く納めることになってしまいます。
⑵ 全ての税理士が詳しいとは限らない
相続税の申告及び納税は難しいことが多いので、税理士に依頼される方がほとんどです。
しかし、税理士資格を持っているからといって、相続税の申告に慣れているわけではありません。
実際、年間の相続税の申告件数が数件である税理士がほとんどです。
相続税の申告に慣れていなければ、間違いが発生することもあります。
相続税の計算方法や特例の適用要件については、かなりの頻度で変更がありますので、毎年の税制改正をしっかり把握しきれていない税理士が多いのが実情です。
3 相続税の払い過ぎと税務署
もし、評価額を間違えて多めに相続税を支払ってしまった場合でも、税務署が正しい金額を教えてくれて、相続税も返してくれると考えている方もいらっしゃいます。
しかし、税務署は、相続税が過少である場合には、税務調査を行い、追徴課税をすることが多いのですが、相続税が過大の場合には、特に何も指摘をしません。
そのため、納税者も払い過ぎに気付かず、放置されてしまうという事態が生じます。
このような事態が生じないように、相続税に詳しい税理士に申告書の作成を依頼することをおすすめします。
相続税申告に関する書類
1 相続税申告ではどのような書類が必要になるのか

家族が亡くなりその相続人が相続税の申告をする必要がある場合、どのような書類を集めなければならないか、よく分からないという方は多いです。
相続税申告に必要な書類は膨大な量になることが多く、相続財産によって集める書類の種類も変わってきます。
必要となる書類を大まかにまとめると、以下のように分類されます。
- ・相続税申告書
- ・被相続人の相続人関係の書類
- ・相続財産関係の書類
- ・債務・葬式費用に関する書類
それぞれの書類について、簡単にご説明いたします。
2 相続税申告書について
相続税申告書の書き方や用紙は、税務署でもらうことができます。
相続人自身が手書きで申告書を作成することもあるようですが、税理士に頼む方が大半のようです。
理由として、相続税申告書自体の作成が難しいこと、後述する必要書類がよく分からないこと等が考えられます。
相続税申告書は、相続の開始を知った日の次の日から10か月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する税務署に提出します。
3 相続税申告と被相続人の相続人関係の書類
相続税申告の際には、相続人が何人いるかということが重要になってくるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
また、財産が未分割の状態で申告するケースでなければ、遺言書か遺産分割協議書のコピーを添付します。
遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを示すために、相続人全員の印鑑証明書も必要になってきます。
上記の他にも、相続時精算課税贈与がある場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票が必要となります。
4 相続税申告と相続財産関係の書類
相続財産の中に不動産がある場合には、不動産の所有関係や固定資産税評価額を示す書類が必要となります。
具体的には、名寄帳、納税通知書の課税明細書、固定資産税評価明細書等の書類や全部事項証明書が必要です。
また、土地が不整形の場合には、公図や地積測量図など土地の形状を示す書類が必要となりますし、不動産を他人に貸している場合には、賃貸借に関する書類を準備しなければいけません。
相続財産の中に預貯金がある場合には、相続開始日時点の被相続人名義の残高証明書が求められます。
通帳のコピーを提出することもあるようです。
定期預金の利息も相続財産となります。
有価証券があれば、有価証券の残高証明書が必要となります。
その他にも財産があれば、必要書類も変わってきます。
5 相続税申告と債務・葬式費用
被相続人に借金や未払債務がある場合には、それを証明する書類が必要になります。
例えば、未払いの固定資産税があれば、それは債務となります。
また葬儀費用としては、葬儀関係の費用の領収書やお布施のメモ等が必要になってきます。
6 相続税申告は税理士にご相談ください
上記のように、相続税申告のために必要な書類は量も種類も多くなります。
必要書類を調べるところから始めるとなると、時間と労力がかかり大変です。
申告に不安をお持ちの方は、お早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続税を申告・納付する義務者
1 相続税の申告について

相続税は、原則として、相続財産が基礎控除額を越えている場合に発生します。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」という計算で導き出される金額です。
例えば、相続人が3人いれば、基礎控除額は4800万円となります。
相続財産の中には、課税対象となる財産とならない財産があります。
そのため、何が相続財産になるのかを把握しなければいけません。
また、相続財産に土地がある場合は、それを適切に評価しなければいけませんが、そのためには、専門的な知識及び豊富な経験が必要になることもあります。
2 相続財産の取得者と相続税の納税義務者
相続税を納税する義務がある方は、相続人だけでなく、相続財産を取得した相続人以外の者も含まれます。
また、遺留分を請求し、財産を取得した相続人にも、相続税を納税する義務があります。
なお、保険金は相続財産ではありませんが、相続税法上は、みなし相続財産として相続税が課税される財産となるため、非課税枠を越えた、もしくは非課税枠の適用がない保険金の受取人は、相続税を納税する必要があります。
3 生前贈与と相続税の納税義務者
相続時精算課税制度の適用を受けた財産を取得した相続人は、相続財産を取得したわけではありませんが、相続税の納税義務者となります。
また、相続開始以前の一定期間内に生前贈与を受けた相続人も、相続財産を取得したとは言えませんし、相続時精算課税制度の適用を受けた財産を取得したとも言えませんが、相続税を納税する必要があります。
このように、相続財産を取得していないとしても相続税の納税義務者となる場合がありますので、注意が必要です。
4 相続税の納税義務者と税額軽減の特例等
相続税には、税負担を軽減するための各種特例や控除があります。
これを利用することで、相続財産を取得した相続税の納税義務者であっても、相続税を納めなくてよくなるケースがあります。
例えば、配偶者であれば、配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることにより、相続税を納める必要がなくなります。
また、未成年者や障がい者であれば、相続税額にもよりますが、未成年者控除、障がい者控除の適用により納税の必要がなくなる場合もあります。
相続税が全体でどの程度かかってくるのか、相続税の納税義務者は誰か、その各納税義務者がいくら相続税の納付をする必要があるのかは、相続人の人数や相続財産の内容・金額等によって異なります。
また、特例を適用した結果、相続税の納付が必要なかったとしても、相続税申告期限までに相続税申告書を提出することが、特例の適用を受ける条件となっているものもありますので注意が必要です。
ご不安な方は、税理士にご相談することをおすすめします。
相続税と障害者控除
1 障害者控除とは何か

障害者控除は、85歳未満の障害者である相続人の相続税が控除される制度です。
相続人が障害者の場合、健常者の相続人と比べ、親等が亡くなった後に生活を保障する必要性が高いこと、また、医療費等の負担が多額になることが予想されます。
そのような事情から、障害の程度に応じて、一定額相続税を控除しようという制度が障害者控除なのです。
相続財産の額から一定金額を控除するのではなく、算出された相続税額から直接控除できるので、税金面の負担が非常に軽くなる制度です。
2 障害者控除を受けるための要件
控除を受けるための要件として、以下の3点があります。
①相続財産等を取得した時に日本国内に住所があること
②相続財産等を取得した時に障害者であること
③相続財産等を取得した人が法定相続人であること
なお、相続放棄があった場合には、相続放棄がなかったものとした場合に相続人である人が、③の要件の法定相続人にあたります。
例えば、相続放棄した障害者である相続人が生命保険金を受け取っていた場合には、障害者控除を受けることができます。
生命保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産であり、受け取ることはみなし遺贈となります。
3 相続税と障害者控除の額
障害の重さによって控除される額が変わります。
障害の重さは2種類で、一般障害者と特別障害者があります。
- ・一般障害者の場合の控除額
- ・特別障害者の場合の控除額
(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円
(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円
一般障害者の控除額と比較して倍の控除額となります。
なお、相続開始日の障害者の年齢は、満年齢でカウントし、切り上げたりはしません。
相続開始日の相続人の年齢が75歳11か月だとしても、例えば一般障害者の場合であれば、75歳を85歳から差し引いて、100万円の控除を受けるという計算になります。
4 相続税と障害者の区分
一般障害者と特別障害者の範囲は、相続税法基本通達19の4-1及び19の4-2に詳しく説明されています。
大まかに説明をすると、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級である方、身体障害者手帳の障害の程度が3級から6級までである方が一般障害者にあたります。
特別障害者は、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級である方、身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級である方があたります。
他にも、市区町村長等の認定を受けている場合には、障害者控除の適用を受けることができる可能性もありますので、詳しくは税理士に確認することをおすすめします。
5 相続税申告と障害者控除
障害者控除を適用した結果、相続税を納める必要がないとなったときは、相続税の申告は不要となります。
一方で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用の結果、相続税が発生しないとしても申告が必要となります。
同じように相続税がかからないという結果になっても、申告が必要かどうかが異なり、本来であれば申告が必要だったにもかかわらず申告していないと、ペナルティが課されるおそれがありますので、注意が必要です。
そのほか、障害者控除やその他の制度について疑問点がある場合は、税理士に確認することをおすすめします。
名古屋にお住まいで相続税の申告についてお困りの方は、一度当法人までご相談ください。
相続時精算課税制度について
1 相続税申告と相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、原則として、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与する場合において、累計2500万円を限度に、贈与税を支払わなくて済むという制度です。
ただし、2500万円を超えて贈与する場合には、一律20%の税率を乗じた贈与税がかかります。
また、贈与者である父母または祖父母が亡くなった場合には、その時点での相続財産にこの制度を選択して贈与した財産の額を加えた額が課税財産となり、相続税の計算をすることになります。
なお、相続税が発生する場合には、相続税精算課税制度を選択した後に納めた贈与税の額を控除することが可能です。
そのため、相続税申告をする場合には、相続時精算課税制度を適用した贈与財産がないかをしっかり確認する必要があります。
参考リンク:国税庁・相続時精算課税制度のあらまし
2 相続税対策と相続時精算課税制度
上記のように、例えば、2000万円の贈与の際に、相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、相続開始時点での相続財産に2000万円を加算して、相続税を計算することになります。
このため、贈与をしてもしなくても、相続税の計算の基礎となる財産額に含まれてしまうこととなりますので、金銭を贈与する場合には、相続時精算課税制度は相続税対策として有効なものではありません。
しかし、相続財産に加算する金額は、贈与時の金額で固定となりますので、贈与時の金額よりも値上がりする財産については、相続時精算課税制度を選択することにより、相続税対策をすることができます。
例として株式が挙げられます。
例えば、非上場会社の株主が、業績が低迷し、株価が低くなっている時に、相続時精算課税制度を選択して贈与を行ったとします。
その後業績が回復し、相続開始時点では株価評価が上昇していたといった場合には、相続税の計算においては、当該株式は、贈与時の低い金額で評価することになるため、納める相続税の額を少なくすることができます。
とはいえ、実際には、確実に値上がりが見込めるような財産であるかどうかは予想できないことが多く、このような側面から相続時精算課税制度を相続税対策として有効活用できる場面は、あまり多くないと考えられます。
3 相続時精算課税制度のメリットを最大限享受できる人
一方で、例えば、贈与前の資産の総額が基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)以下という方については、相続時精算課税のメリットを最大限享受できます。
上記のような方が、例えば、自分の子どもに1000万円贈与したいという時に、相続時精算課税制度の適用を受ければ、贈与税がかかりません。
また、相続の際には、1000万円を繰り戻して相続税を計算しても基礎控除額以下となり、相続税の申告をする必要もありません。
このように、もともと相続税がかからない方が、財産を相続の前に先渡ししたいという場合には、相続時精算課税制度のメリットを最大限享受できるといえます。
ただ、この場合であっても、相続時精算課税制度以外に有効活用できる特例がないか、検討はした方が良いと思います。
例えば、親や祖父母から子や孫に対して、住宅取得資金を贈与した場合は、住宅取得資金の贈与の特例という制度によって、相続時精算課税制度を利用せずとも贈与税がかかりません。
参考リンク:国土交通省・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
このように、他の特例を利用することができる場合には、あえて相続時精算課税制度を利用するメリットは大きくはないといえます。
4 相続時精算課税制度の基礎控除
この制度を利用した場合、暦年課税には戻れなくなるため、相続時精算課税制度のデメリットの一つとして、毎年110万円まで贈与税の基礎控除があることを利用した暦年贈与による相続税対策ができなくなってしまうという点がありました。
しかし、法改正により、令和6年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が創設されました。
そのため、年間110万円以下であれば贈与税はかからず、相続時精算課税の総額にも含まれないことになります。
今回の法改正によって、事実上この点のデメリットはなくなったといえるでしょう。
相続税とマンション敷地の評価
1 マンションを建てた場合の土地の相続税評価額

通常、土地の相続税評価額は、路線価または固定資産税評価額に倍率をかけて算出します。
路線価及び倍率は、国税庁のホームページから確認することができ、毎年7月にその年の情報が更新されます。
参考リンク:国税庁・路線価図・評価倍率表
この評価額は、更地や自己の居住用に一軒家を建てているなど、自分のために自由に使用することのできる場合の額となります。
賃貸マンションのように、自己所有の土地に自己所有の建物を建築し、他人に貸す場合は、上記の場合と比べて、利用が制限されているといえます。
また、マンション敷地のように広い土地で、500平方メートルを超えるような場合であれば、地積規模の大きな宅地の評価の要件を満たすことで、さらに評価を減額することができます。
参考リンク:国税庁・地積規模の大きな宅地の評価
そのため、マンション敷地の場合は、更地等よりも相続税評価額が下がることになります。
2 相続税評価額と貸家建付地
マンション敷地のように、自己所有の土地に自己所有の建物を立てて他人に貸している土地を「貸家建付地」といいます。
貸家建付地の価格は、「自用地(他人が使用する権利のない土地)としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で算出します。
借地権割合は、他人が建物を建てるために地代をもらって土地を貸した場合、所有者が土地を自由に使用できないことによる評価減の割合をいいます。
借地権割合は地域によって異なり、国税庁のホームページで確認できます。
借家権割合は、建物を貸した場合に、所有者が建物を自由に使用できないことによる評価減の割合のことをいいます。
賃貸割合は、課税時期において賃貸されている各部屋の床面積合計がマンションの各部屋の床面積合計に占める割合をいいます。
中には、マンションに、オーナー自身が使用している部屋がある場合や、空室になっている場合があるので、賃貸割合の算出には注意が必要です。
3 相続税評価額と小規模宅地等の特例
マンション敷地は、小規模宅地等の特例の中の貸付事業用宅地にあたりますので、その他の要件を満たせば、50%評価を減額することができます。
ただし、200㎡までの限度面積要件があることに注意が必要です。
このように、マンション敷地の評価には様々な知識が必要となります。
相続に慣れており、不動産評価に関する知識がないと、マンションの相続税評価額を正確に算出することは難しいと思いますので、相続税に関してお悩みの方は税理士に相談することをおすすめします。